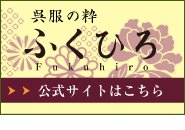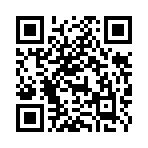スポンサーサイト
姉妹編もマニア度爆走っ! 別冊太陽 『 日本の自然布 』
2012年02月27日
別冊太陽 『 日本の布 原始布探訪 』 すっごい 情熱大陸本 でしたぁ
もォ おなかいっぱい ~(´▽` )~ しかし ・・・ 実は あったのです ・・・
空前絶後かと思われた あのマニア本に 姉妹編 が・・・ どぇぇぇ~ <(゜□゜;)>
別冊太陽 『 日本の自然布 』 2004年の出版ですから 実に15年ぶりの姉妹編です。
『 厚司織 〈 アットウシ織り 〉 』
北海道日高地方 アイヌの人々によって 大切に織り継がれてきた あまりに稀少な 古代原始布 ・・・
「オヒョウ」という樹の皮を繊維状に裂き 紡(つむ)いで糸にして織るという超絶技巧! 絶品の風合いです・・・
邪気を祓(はら)う アイヌ文様を 切伏せと刺繍 で表現。「切伏(きりぶ)せ」とはいわゆる アップリケのこと。
それにしてもオヒョウ採集から糸つくり・織りまで・・・ こんな珍しい厚司織の写真 初めて見ました。Σ(P_=;)
『 紙布 (しふ) 』
ええ~っ!? 紙で衣を織ったら すぐに破けちゃいませんかァ!? (+w+;)
いえいえ 「紙布」って 思ってるよりかなり丈夫なんですよ。 写真は原料の楮(こうぞ)を
巨大蒸し器(ジブリのSFアニメかっ?) で蒸してるところ。 in 宮城県白石です。(vv)
奈良県東大寺の「 紙衣づくり 」も紹介されてます。二~三月の酷寒のころ 紙衣をまとう習わしがあるそうです。
江戸時代の武士の裃(かみしも)や袴(はかま)も紙布を使ったものが。。。 強度は心配ないですよ。 (=w=)
『 天蚕 (てんさん) 』
日本の野生のカイコ いわゆる 野蚕(やさん) がみられるのは 長野県信州松本は 安曇野の高原のみ ・・・
信州松本の野蚕 「 天蚕 」が吐く糸は体色と同じく エメラルドの輝き。100%天蚕糸 は目ン玉飛び出ます。
『 喜如嘉の芭蕉布 』
「厚司織」が古代原始布の北の横綱だとしたら 「芭蕉布」は間違いなく南の横綱です。
芭蕉布の 「 海晒(ざら)し 」 の写真は 珍しいです。 見たことがない ・・・。
海水と川水が混じり合う浦内川の河口付近は 海晒しに最も適しており 発色のよい芭蕉布ができるそうです。
た、 平良先生 、 お若い っっ !!
姉妹編もマニア度爆走っ! 情熱大陸大噴火でありましたァ!!(//∀//)
めずらしキモノ本 別冊太陽 『 日本の布 原始布探訪 』
2012年02月24日
別冊太陽 『 日本の布 原始布探訪 』 平成元年 の出版物 ・・・
ええ? 「 榀布 (しなふ)」 実物見本っ!? 出ました 情熱大陸っ!
深夜 出版社編集部で 榀布の生地を ちょきちょき ぺたぺた 貼り貼り・・・ 凄い熱意 涙が出ます !
さて 榀布 (しなふ) って一体なんでしょう ?
山形県との県境 新潟県山北村に 古来より産する 日本伝統の 古代原始布 なのです。
榀の木の樹皮を 細かく繊維状に裂いて 織り出すのです。
このような日本各地に伝わる 稀少な古代原始布を 一堂に網羅した写真集 なのです。
『 藤布 (ふじふ) 』
どこの国の原生林ジャングルかと思いきや 京都府宮津市 丹後半島の山間部なのでした。
新緑五月に咲きほこる藤の花。その固くて強靭な蔓(つる)を裂いて糸にするのだから タダ事ではないです!
でも不思議と原始布の中では特に軽くしなやか。ふたりの媼(おうな)が秘かに織り継いでるだけだそうです。
『 葛布 (くずふ) 』
静岡県 掛川 に古くから産する 古代原始布 「 葛布 」。秋の七草の葛の蔓(つる)で織り出されます。
葛飾北斎の錦絵 『 掛川 』。 葛布は東海道の宿場町である掛川の名産。
女のひとが抱えているのが 葛布の反物ですよ~ (^^)
葛布の帯は さらりと 軽く しなやかで 単衣の織帯に最高です。
『 別冊太陽 』 独走の 原始布マニア写真集 実は 続編が存在した !?
ええ~っ ??? <(゜□゜;)> 以下次号 !!!
ツイッター & フェイスブック 始めました。
2012年02月24日
インターネットには 心もとないボクですが 。。。始めてしまいました ・・・
ツイッター に フェイスブック ・・・ 大丈夫でしょうか~? (^□^;)
ツイッター @gofuku_fukuhiro
フェイスブック 「 福治 督浩 」
どうぞ よろしく お願い申し上げます。 m(_ _)m
Posted by ふくひろ 若旦那 at
13:06
│Comments(2)
竺仙(ちくせん)浴衣 2012 新作200柄 受注会 後篇
2012年02月18日
絹紅梅、 松煙染め と べんがら染め、 奥州小紋 に 紅梅小紋 ・・・
竺仙のなかでも高級な部類に入るこれら特殊染め浴衣になぜか注文が集中します。おそらく夏期の呉服店頭でも
著しく出現率、遭遇率が低いのがこの竺仙の特殊染め浴衣・・・。さらには浴衣というよりも「夏キモノ」「単衣もの」
といっても通用するグレードの高さが人気の秘密でしょう。帯次第で「おしゃれ着物」の雰囲気を醸し出しますよ。
『 紺地 柳に燕(つばめ) 』 『 紬ゆかた 破れ七宝 』
飛燕の柄も竺仙の定番。颯爽(さっそう)と飛び交うさまは粋で涼しげです。紺地の「柳に燕」は初めてみました。
青地に織り縞の紬ゆかたの生地はさらりとして着映えがします。とくにこの「破れ七宝」は帯が合わせやすいです。
『 べんがら染め 葡萄 』 『 深海の金魚 』
べんがら染め新作は 前回の「源氏香」と もうひとつがこの「葡萄」。 かすれた紅色がなんとも味わい深い逸品。
深海にはもちろん金魚はいませんがなんとなく。。。(>▽<) 黒地に金魚が浮かんで レトロモダンな雰囲気。
『 斧琴菊(よきこときく) 』 『 奥州小紋 万年青(おもと) 』
歌舞伎好みの男ものですねえ。 「 善(よ)きことを聴く 」 という とても縁起のよい 語呂合わせなのです。
この万年青も不老長寿のおめでたい柄。季節ノープロブレムの多年草ですが秋にはかわいい実が赤く色づきます。
『 芍薬(しゃくやく) 』 『 松煙染め すすき取り 菊に萩 』
「立てば芍薬 座れば牡丹 ・・・」といいますが 芍薬の柄自体は珍しい。この浴衣で立ち姿美人になれそうです。
渋く枯淡の雰囲気を醸し出す松煙染めですが 薄(すすき)で柄が引き締まり 大胆で斬新な古典柄になってます。
『 理想的 藤の花 』 『 とんぼ かくれんぼ 』
大きさといい色といい まさに理想的な藤の花です。藤の花って 可憐で凛々(りり)しいイメージがありませんか?
蔓草(つるくさ)の間で 蜻蛉(とんぼ)がかくれんぼしています。トンボがいるのぱっと見わからなかったんですよ。
『 藍鼠紅梅小紋 貝合わせ 』 『 砂色絹紅梅 麻の葉 』
紅梅小紋は 鮮やかな納戸ブルーが主流ですが ごくたまに この藍鼠(あいねず)色が使われることがあります。
なんとも上品な色ですね。貝合わせは蒔絵や金箔をあしらった貝殻を使った 平安貴族の雅(みやび)な遊びです。
絹紅梅でサンドベージュ色は 夏物の小紋か夏紬に見えますね。 砂色絹紅梅は もうひとつドット柄もありました。
『 こどものゆかた 西瓜 スイカ 』
美味しそうなスイカです。箸休めのデザートです。(^ー^)
『 絹紅梅 牡丹唐草 』
絹紅梅をお召しになった方に聞くと風がす~っと通ってとても涼しいそうですよ。
まさに “ 風を孕(はら)む夏衣 ”・・・ この 「 牡丹唐草 」は もォ言うことなし、文句なしの柄ですね~
竺仙(ちくせん)浴衣 2012 新作200柄 受注会 中篇
2012年02月16日
何年か前に 婦人雑誌や CMメディアで 素敵な浴衣に ひとめぼれ! ところが ついつい買い逃し 。。。
いまだに あの浴衣(ヒト) が忘れられず ・・・ 『 浴衣漂流 』 してしまっている方 けっこう 多いです ・・・。
そんな方はいちどのぞいてみてください ふくひろ 竺仙浴衣 新作200柄 冬の受注会
忘れられない あの浴衣(ヒト)に ふたたび 出逢えるかも知れませんよ ・・・ ?

『 翡翠グリーンの松煙染め 唐草風 』
この図案は 2010年 女優の小雪さんが 着用していた柄なんです。 実は ぼく自身がひとめぼれした
唐草文様なのでした。(^□^;) またココで出逢えるとは。。。! 小雪さんが着ていたのは 墨鼠色の
正当派松煙染め だったんですが こんな翡翠(ひすい)グリーンは初めてみましたね。 オーラ 漂ってます ・・・


『 笹にふくら雀 』 『 綿絽に青牡丹 』
「ふくら雀(すずめ)」の柄も 竺仙は他の追随を許しませんね。 この図案は初めて見た気がします。
白地に青い牡丹 なんて なんとも鮮烈ではないですか。 図柄は品格がありますが 絽目が涼感を誘います。


『 鬼灯 (ほおずき) 』 『 輪繋(つな)ぎ 奥州小紋 』
「ほおずき」が なぜ 子供もの の柄かといえば 昔は 口に噛んで ブ~ブ~鳴らす 遊び道具だったからです。
「輪繋ぎ~」は確か4,5年前の 雑誌「七緒」の浴衣特集 で見かけた覚えがあります。久方ぶりのリバイバル!
小柄なモデルさんにも しっくり馴染む飽きのこない柄で 博多半巾でも名古屋帯でも合う 大活躍の浴衣でした。


『 桜に羊歯(しだ) 』 『 男もの 蛸(たこ) 』
桜に羊歯? って珍しいカップリングじゃないですか。 羊歯は 長寿・一家繁栄 のおめでたい文様です。
タコの柄って初めてです。(゜□゜;) やはり“ 葛飾北斎の蛸 ”なんでしょうか? 粋な男の遊び柄ですね。


『 紬ゆかた 葡萄(ぶどう) 』 『 納戸色綿絽 御簾(みす) 』
白グレーの紬ゆかたは着やすいって方、多いですよね。たしかにさらりとセミカジュアル。葡萄は豊穣の吉祥文様。
御簾とは“すだれ”のこと。平安王朝の典雅な趣き。 納戸ブルーのさざめく絽目と なんともベストマッチングです。

『 松煙染め 色紙取りに百華 』
これぞ 純正松煙染め ・・・ 渋さの中にも味があり。墨ぼかしの濃淡がいいですねえ~ 竺仙の独壇場です・・・

『 絹紅梅 杜若(かきつばた) 』
中篇のトリを務めますのは見事に咲きほこった杜若。合い間に板の橋が渡れば「 八橋 やつはし 」になります。
なんとか “ 中篇 ” まで たどり着きました~
がんばって “ 後篇 ” に つづきま~す (((( ≧▽≦ ))))
いまだに あの浴衣(ヒト) が忘れられず ・・・ 『 浴衣漂流 』 してしまっている方 けっこう 多いです ・・・。
そんな方はいちどのぞいてみてください ふくひろ 竺仙浴衣 新作200柄 冬の受注会
忘れられない あの浴衣(ヒト)に ふたたび 出逢えるかも知れませんよ ・・・ ?
『 翡翠グリーンの松煙染め 唐草風 』
この図案は 2010年 女優の小雪さんが 着用していた柄なんです。 実は ぼく自身がひとめぼれした
唐草文様なのでした。(^□^;) またココで出逢えるとは。。。! 小雪さんが着ていたのは 墨鼠色の
正当派松煙染め だったんですが こんな翡翠(ひすい)グリーンは初めてみましたね。 オーラ 漂ってます ・・・
『 笹にふくら雀 』 『 綿絽に青牡丹 』
「ふくら雀(すずめ)」の柄も 竺仙は他の追随を許しませんね。 この図案は初めて見た気がします。
白地に青い牡丹 なんて なんとも鮮烈ではないですか。 図柄は品格がありますが 絽目が涼感を誘います。
『 鬼灯 (ほおずき) 』 『 輪繋(つな)ぎ 奥州小紋 』
「ほおずき」が なぜ 子供もの の柄かといえば 昔は 口に噛んで ブ~ブ~鳴らす 遊び道具だったからです。
「輪繋ぎ~」は確か4,5年前の 雑誌「七緒」の浴衣特集 で見かけた覚えがあります。久方ぶりのリバイバル!
小柄なモデルさんにも しっくり馴染む飽きのこない柄で 博多半巾でも名古屋帯でも合う 大活躍の浴衣でした。
『 桜に羊歯(しだ) 』 『 男もの 蛸(たこ) 』
桜に羊歯? って珍しいカップリングじゃないですか。 羊歯は 長寿・一家繁栄 のおめでたい文様です。
タコの柄って初めてです。(゜□゜;) やはり“ 葛飾北斎の蛸 ”なんでしょうか? 粋な男の遊び柄ですね。
『 紬ゆかた 葡萄(ぶどう) 』 『 納戸色綿絽 御簾(みす) 』
白グレーの紬ゆかたは着やすいって方、多いですよね。たしかにさらりとセミカジュアル。葡萄は豊穣の吉祥文様。
御簾とは“すだれ”のこと。平安王朝の典雅な趣き。 納戸ブルーのさざめく絽目と なんともベストマッチングです。
『 松煙染め 色紙取りに百華 』
これぞ 純正松煙染め ・・・ 渋さの中にも味があり。墨ぼかしの濃淡がいいですねえ~ 竺仙の独壇場です・・・
『 絹紅梅 杜若(かきつばた) 』
中篇のトリを務めますのは見事に咲きほこった杜若。合い間に板の橋が渡れば「 八橋 やつはし 」になります。
なんとか “ 中篇 ” まで たどり着きました~
がんばって “ 後篇 ” に つづきま~す (((( ≧▽≦ ))))
竺仙(ちくせん)浴衣 2012 新作200柄 受注会 前篇
2012年02月14日
おまたせしましたっ ! 竺仙浴衣 2012年 新柄 やっと到着ですっ !
なんでこんな寒~い時期に 竺仙浴衣なのかと申しますと 雑誌・CM・メディアなどに 浴衣美人が闊歩し始めて、
あ~ こんなのかわいい~ これ着てみたいなァ ・・・ などと 話に花が咲く季節(ころ)には もうすでに 。。。
遅~いっっ!! 追跡・探索 不可能な浴衣 まことに多いのです。 (^□^;)
ぼくら呉服屋が浴衣の柄見をする雪降る二月なら 竺仙新作を 100%コンプリート、チェック可能なのです!
“ こたつ DE アイス ” を楽しむ心地で 竺仙浴衣 今年の新作 ご覧くださいませ ♪
『 千鳥 三題 』
千鳥(ちどり)は竺仙の定番得意わざっ!こんなにいきいきと 大空を舞う千鳥は よそではついぞ見かけません。
そこは老舗の強味です。どっちの千鳥が好きですか?えっ?一題足りない?三つめはとっておきデス(≧w≦)
「浴衣の王者 ・ 絹紅梅(きぬこうばい)」 の千鳥です。絹紅梅は絹地に太い綿糸を格子状に織り込んだもの。
ほとんど正絹の夏きものですねえ。頭に飾り羽根までたくわえたこの千鳥、 さすが凛々しく気品にあふれてます。
『 納戸ブルーのホタル 』 『 夜明けの朝顔 』
竺仙・必殺の決め色、納戸(なんど)色は藍甕の緑みのある清々しいブルー、蛍の乱舞にぴったりなのデス。。。
「玉むし」は竺仙の多色使いカラフルシリーズ。黒地の朝顔って珍しくないですか?ちょっと大人の雰囲気かも。。。
『 ウサギとカメ 』 『 風花(かざはな) 』
子供もの浴衣、やはり男の子の柄?お子さまに「ウサギとカメ」の話をゆ~っくりと聞かせてあげたいですねえ~
風に舞う花のように 涼感溢れる浴衣です。淡彩ですが図案に動きがあるので すっきり華やかになると思います。
『 蜻蛉か松葉か 』 『 番傘に隈取(くまど)り 歌舞伎文 』
大空を突き進むトンボか 千々に乱れる松葉か どっちなんでしょう?どちらにしてもシンプルかつ大胆で斬新です。
江戸好み・歌舞伎文様は 粋な柄で人気があります。男ものですが いなせな女性も 女ものでお召しになります。
『紬ゆかた 雪輪に地紙 』 『 紅梅小紋 蔓(つる)唐草 』
紬ゆかたは 浴衣なれど 単衣の時期でも キモノっぽく見えるすぐれもの(しかも涼しい)。柄にも重みがあります。
「紅梅小紋」とはいわゆる「綿紅梅」。絹紅梅と同じ織り方ですが こちらは綿100%。もちろん風合いも違いますが
紅梅小紋の生地が好きなヒトもとても多いです。こういう小付けの柄は着姿が美しく なんとも涼しげですよねぇ~
『 べんがら染め 源氏香 』
この 「 べんがら染め 」の 紅色は なんとも 雅味があっていいですねえ。 源氏香の暈(ぼか)した加減が
なんともいえず 風雅です。 これはちょっと ・・・ かなりの 傑作かもしれませんぞ 。。。 (゜∀゜;)
やっぱり ギリギリでした~(><) 中篇につづきま~す!
絶品っ! 漆箔( うるしはく )大唐草 in 渋好みの会
2012年02月12日
「 渋好みの会 」 巻頭を飾りしは ・・・ 幽玄 玄妙なる 逸品 ・・・
譽田屋源兵衛 謹製 手織袋帯 「 本漆箔 大唐草 」
写真ではわかりにくいのですが 不思議なことに 角度や光線によって 色や 質感 帯の表情 が変わるのです。
鉱物に近い質感を醸し出すため 幾種もの漆箔を 多層に織り重ねて 試行錯誤の末 完成したものだそうです。
まさに “ 織りの多重奏 ” 「 渋好み の 極(きわ)み 」 ではないですか 。。。 (゜□゜;)
「 玉子色(たまごいろ)の 織り更紗袋帯 」 墨色ブラックの 野蚕糸・栗繭紬 に合わせてます。
JAPAN BLUE 藍染めの縞に 。。。
博多織の八寸名古屋帯 を 。。。 粋(いき)な 着こなしも 渋好み のひとつ 。。。
“ 渋好み ” は お洒落着ばかりじゃありません。すっきり淡彩 刺繍の付け下げ着尺に 若松菱 礼装袋帯
婦人雑誌では よくみかける すっきり淡彩礼装着 ですが いざ探すと なかなか ないんですよねぇ ~
派手でもなく さりとて 地味でもなく エレガントで気品がある淡彩礼装着、 出現率 極めて低いのデス。。。
竺仙浴衣200柄 やはり まだまだ 到着しません 。。。 <(ー_ー;)>
次回は 竺仙2012新柄特選 を いち早くご紹介しようと思ってましたが。。。
例年通り ギリギリのアップに なりそうですっ! (゜∀゜;) パソコン打つのが遅いんデス・・・
“ 透明感 あっさり コーディネート ” in 渋好みの会
2012年02月07日
『 渋好みの会 』 ( 2/15 ~ 2/22 ) 今年のテーマは 。。。
“ 透明感 あっさり コーディネイト ” ・・・にしようかなぁ~と思ってます (^ー^)
写真の 無地感覚の あっさり紬は 緯(よこ)糸に インド・アッサム地方に生息する ヤママユの野蚕糸 と
栗の葉を食する蚕 の 栗繭糸 を 織り込んだ ざっくりとした風合いの 野趣溢れる 野蚕無地紬 なのです。
染抜一ッ紋の綸子色無地 では 友人同士の気軽な食事会には ちょっと かしこまりすぎかなァ? ・・・ とか
略式のパーティーではあるけれど 総絣の本格伝統工芸紬では やはり お洒落着 になってしまう? ・・・ とか
そういうムズカシイ場面で活躍するのが セミフォーマル ・ セミカジュアルの スーツ感覚、
野蚕糸無地紬 をベースにした “ 透明感あっさりコーディネイト” なのです。
↑(v_v ) 上の合わせ方、銀糸を織り込んだ辻ヶ花文様の袋帯 なんですが ややカジュアルでしょうか?
象牙色アイボリーの淡彩無垢(むく)の唐草袋帯 です。これなら 振り子は ややフォーマルに傾きますね?
少し地味なら パステル調の パープルピンクか ほのかなクリームの 帯締めで 彩りを・・・ (^v^)
エメラルドの 洋花更紗 =全通総柄= 塩瀬染め名古屋帯 です。
雑誌 「 美しいキモノ 」 で 菊川 怜 さん も着用してました。
この帯だと 友人同士の気軽な食事会、女子会にも 形式張らない & エレガントな着こなし が できますね。
この “ 栗繭・野蚕糸 無地紬 ” 今回 特別記念価格で お出しするんですが。。。
『 アヴァンティ 』 等 情報誌で 公表してますので 言っちゃいましょうかぁ。。。?\(^□^;)/
胴裏・八掛つけた 袷(あわせ)仕立て上がり で 特別価格 155,000 円(税込) 。。。ですっっっ
かなり 思い切った値段だ と思んですが 。。。まァ、 気になったら 「 渋好みの会 」 見においでください。
|(_ _)| 「 竺仙浴衣 新作200柄 受注会 」 も同時に 開催しております。
さいごは お茶の間 テレフォンショッピング みたいに なっちゃいました 。。。<(-_-;)シツレイシマシタ~
帯揚げ ちらちら コレクシオン ~宝尽くしからサイケまで ~
2012年02月03日
帯揚げ って 。。。 帯の間から ちらちら カオだすくらいですけど ~
仕上げの色合わせっ!やっぱり 凝りたいアイテム ですよね~ (≧▽≦)
。。。 というわけで “ 帯揚げ ちらちら コレクシオン” で~す !!!
淡彩ベージュの 『格天井』 春色ピンクの 『七宝に鎧縅(よろいおどし)』
写真では 判りにくい 繊細で ほんのりほのかな 淡い色づかいが 帯揚げでは 最適ですねぇ (≧w≦)
“礼装帯揚げ”では 主張しすぎない ふわっと薫る 華やぎ彩り、 さらに 気品と格調をたたえていなくては。。。
サーモンピンクに 『絞り・宝尽くし刺繍』 スカイブルーに 『立涌(たてわく)地紋起こし』
絞りに刺繍なんて キモノに施したら かなりの高級品・・・帯揚げの世界では そんな贅を凝らした匠の手わざを
惜しげもなく使っている点が凄いっ!というか不思議なトコですよねぇ?ど~ゆ~ワケなんでしょう? Σ(ー_ー;)
「地紋起こし」は わざわざ別織りした白生地に染めを施す技法ですが 着尺でも 最近はみかけなくなりました。
鉄グレー紬地に 『 春色ワンポイント刺繍 』
この帯揚げはスキですね~ このシリーズはどれも素晴らしい中間色、生地もさらさら紬地で 文句ナシですが・・・
あれれ? このワンポイント刺繍(左右2ケ所) 着用して ホントにみえるの? 心配無用です。 (-v-)
この刺繍は帯枕を包んだすぐ両脇に出ます。お太鼓から前に向かって帯揚げが渡ってみえる 絶妙の部分に
唐草刺繍が 左右ふたつ 出ちゃうんですねっ! とっても キュートで なおかつ 斬新であります。 ♪(^ワ^ )
わっ サイケデリックっ!! これも 帯揚げ ですかァ !?
『 縮緬地に染め分け サイケな 帯揚げ 』
はい、帯揚げです ・・・ サイケな帯揚げ ・・・ (゜□゜;) 染めはかなり凝ったものなんですが 奇抜 ですね~
いったいどんなキモノに合わすんでしょうか? こうゆう個性的な帯揚げが必要なコーディネイトもあるんです。。。
合わせてみて おおっ ぴったり! というような・・・どんな組合わせかは即座にはいえませんが。。。 (;¬_¬)
『 猫・ネコ・百ねこ 』 『 煙管(きせる) の 帯揚げ 』
「百ねこ」と書きましたが 実際には “1000匹” 以上いました。猫、ネコ、ねこだらけの帯揚げです。(≧∀≦)
煙管(きせる)の柄って 珍しくないですか? 落語の世界で 出てきそうですね、ちょっと 一服。。。って感じ~
どちらも 紬はもちろん なにより 江戸小紋に 合いますねっ! 粋で いなせで 遊び心満載です。 (+w+)
『 紅色 麻の葉絞り 』 『 ターコイズブルー に 豪華ケンラン大刺繍 』
紅色麻の葉は黒地のすっきりしたキモノに合わすと凄く粋になります。ありそうで見つからないのがこのタイプです。
これはまた 豪華ケンラン、この上なし!こんなボリューム満点の刺繍は見たことありません。重厚感ありありっ!
やはり 十三参りか成人式振袖がいいでしょうねぇ~ 誰もしてないような帯揚げといったらコレでしょう!(・∀・)
帯揚げの世界も なんだか とっても 深ァ~い ですね ~
“ 帯揚げ ちらちら コレクシオン ” これからも ちらちらと 続きま~す
(゜∀゜;)つ、続くんですね。。。
山口源兵衛 vs ビートたけし BS放送 観ましたよォ~
2012年02月02日
満を持して観ましたっ ! 2月1日の 『 たけしアート★ビート 』 !
譽田屋(山口)源兵衛さんの 作品を創り出す気概とパワーの秘密が
垣間(かいま)見えて ・・・ 面白かったァ ~ ((((>w<))))
西陣の職人さんと バトルしながら織り上げた 古今未曾有の逸品 ・・・
まことに独創的な “ 譽田屋浴衣 ”も紹介されました。
「 体 と 考え方 と 着る物 は 全部 つながっている ・・・ 」
着物とは その人の 精神を まとう ・・・ ってことなんですね ・・・
漆縞(うるしじま)・濡羽色(ぬればいろ)の 男もの、 たけしさん とっても 似合ってましたよ。
さいごに 源兵衛さんの ひとこと を ・・・
ものづくりに対する 飽くなきチャレンジ精神 と 純真無垢な好奇心 です。