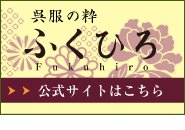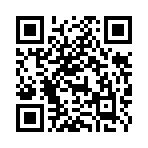スポンサーサイト
なぞの呪文? 「 オリ ・ ソメ ・ ソメ ・ オリ 」
2011年04月27日
【case1: A子さんの場合】
あるとき A子さんは来月のお食事会用のキモノをおばさまと一緒に選んでいました。おばさまはキモノに詳しいのです。
とっても素敵な桜ピンクの無地紬に シルバーグレー地の華紋、ふくれ織りの九寸名古屋帯がありました。
こんな感じです・・・(P-^)↓

カワイイ! A子さんはひとめで気に入りましたが おばさまから おもむろにイエローカードが差し出されました・・・。
「 A子ちゃん、 むかしから 織りの着物には 染めの帯 ってよくいうわ・・・染め帯の方がいいんじゃない? 」
「 ???・・・織りに・・・ 染め・・・? 」 A子さんはどうしていいか わからなくなりました。
【case2: B子さんの場合】
B子さんは友だちと観劇にいきます。 箪笥の中から 空色ブルーの江戸小紋をうきうき 取り出しました。
色無地代わりの準礼装着として金糸の袋帯といっしょに買ってもらったお気に入りなのです。 普段でも着れるように
紋は入れてません。 気の合う友だち同士なので あっさり おしゃれな取り合わせがいいなァと思うB子さん。
金の豪華な袋帯より 大島紬に合わせていた塩瀬の更紗風の染め名古屋帯を締めちゃおう! と思い立ちました。
こんな感じです・・・(P-^)↓

しかし、横で見ていたお母さん、イエローカードです。「 いっしょに買った金の袋帯があったでしょ、アレにしなさい!」
「 ええ~ なんか重たくならない~? 」 「 だって 染めの着物に 織りの帯 って いうでしょう ? 」
「 ??? 染めに・・・織りィィ・・・? 」 B子さんも思考停止におちいってしまいました。
「 織りの着物に 染めの帯、 染めの着物に 織りの帯 」
帯合わせのとき よく耳にする この言葉・・・格言というか、 ことわざというか、 なぞの呪文のように発動して
ぼくのような若輩呉服屋のあたまを長い間、悩ませてきました。 <(ー_ー;)>
お客さまからもよく質問される このことば、 いったい どんな意味があるんでしょうか ???
ぼくが独断で推察させてもらうなら、おそらく この言葉は もっと 広く おおまかな 着物と帯の合わせかた・・・、
強いていうなら ごくごく 基本的な 着物と帯の 「 格 」 のことをいってるんだと思うのです・・・。
たとえば こう 言い換えてみてください。
①『 染めの着物 』 = 訪問着や付け下げの礼装着
②『 織りの帯 』 = 袋帯 礼装用
③『 織りの着物 』 = 紬 つむぎ おしゃれの普段着
④『 染めの帯 』 = 染め帯 おしゃれの普段用名古屋帯
ほら、なんかとてもわかりやすくなったと思いません?
そうです、 キモノの「格」 に忠実に、 ごくごく基本的な着物と帯の取り合わせのことをいってるんですね。
①+②、③+④ の合わせかたは もう一般的なんですけれど
①+④、③+② の合わせかたは絶対ありえないですよね?
あまり ムズカシク かんがえなくていいんです。
A子さんのおばさまも B子さんのお母さんも 着物の「格」からみて正解、正統派の間違いのない帯合わせなのです。
ただ 無地の紬に織り名古屋帯、 江戸小紋に染め帯、という カジュアルな組み合わせは
従来の着物の 「格」 のカテゴリーからはずれた やや新しい傾向の合わせ方なんですね。
礼装着か普段着かの二者択一のなかに セミカジュアル・セミフォーマル の中庸の帯合わせが出てきたんです。
「 オリ・ソメ・ソメ・オリ 」 の呪文があまり効きすぎると ちょいカジュアル派の立場が弱くなっちゃいますよね。
新しい呪文 「 オリ・オリ 」「 ソメ・ソメ 」 もケースバイケースで アリっ ! ・・・ だと思います。
これは ぼくの個人的見解なので みなさんはじめ 同業のキモノびとのひとたちにもご意見お聞きしたいです。
是非是非 コメント お聞かせください。よろしくお願いします。 |(_ _)|
あるとき A子さんは来月のお食事会用のキモノをおばさまと一緒に選んでいました。おばさまはキモノに詳しいのです。
とっても素敵な桜ピンクの無地紬に シルバーグレー地の華紋、ふくれ織りの九寸名古屋帯がありました。
こんな感じです・・・(P-^)↓
カワイイ! A子さんはひとめで気に入りましたが おばさまから おもむろにイエローカードが差し出されました・・・。
「 A子ちゃん、 むかしから 織りの着物には 染めの帯 ってよくいうわ・・・染め帯の方がいいんじゃない? 」
「 ???・・・織りに・・・ 染め・・・? 」 A子さんはどうしていいか わからなくなりました。
【case2: B子さんの場合】
B子さんは友だちと観劇にいきます。 箪笥の中から 空色ブルーの江戸小紋をうきうき 取り出しました。
色無地代わりの準礼装着として金糸の袋帯といっしょに買ってもらったお気に入りなのです。 普段でも着れるように
紋は入れてません。 気の合う友だち同士なので あっさり おしゃれな取り合わせがいいなァと思うB子さん。
金の豪華な袋帯より 大島紬に合わせていた塩瀬の更紗風の染め名古屋帯を締めちゃおう! と思い立ちました。
こんな感じです・・・(P-^)↓
しかし、横で見ていたお母さん、イエローカードです。「 いっしょに買った金の袋帯があったでしょ、アレにしなさい!」
「 ええ~ なんか重たくならない~? 」 「 だって 染めの着物に 織りの帯 って いうでしょう ? 」
「 ??? 染めに・・・織りィィ・・・? 」 B子さんも思考停止におちいってしまいました。
「 織りの着物に 染めの帯、 染めの着物に 織りの帯 」
帯合わせのとき よく耳にする この言葉・・・格言というか、 ことわざというか、 なぞの呪文のように発動して
ぼくのような若輩呉服屋のあたまを長い間、悩ませてきました。 <(ー_ー;)>
お客さまからもよく質問される このことば、 いったい どんな意味があるんでしょうか ???
ぼくが独断で推察させてもらうなら、おそらく この言葉は もっと 広く おおまかな 着物と帯の合わせかた・・・、
強いていうなら ごくごく 基本的な 着物と帯の 「 格 」 のことをいってるんだと思うのです・・・。
たとえば こう 言い換えてみてください。
①『 染めの着物 』 = 訪問着や付け下げの礼装着
②『 織りの帯 』 = 袋帯 礼装用
③『 織りの着物 』 = 紬 つむぎ おしゃれの普段着
④『 染めの帯 』 = 染め帯 おしゃれの普段用名古屋帯
ほら、なんかとてもわかりやすくなったと思いません?
そうです、 キモノの「格」 に忠実に、 ごくごく基本的な着物と帯の取り合わせのことをいってるんですね。
①+②、③+④ の合わせかたは もう一般的なんですけれど
①+④、③+② の合わせかたは絶対ありえないですよね?
あまり ムズカシク かんがえなくていいんです。
A子さんのおばさまも B子さんのお母さんも 着物の「格」からみて正解、正統派の間違いのない帯合わせなのです。
ただ 無地の紬に織り名古屋帯、 江戸小紋に染め帯、という カジュアルな組み合わせは
従来の着物の 「格」 のカテゴリーからはずれた やや新しい傾向の合わせ方なんですね。
礼装着か普段着かの二者択一のなかに セミカジュアル・セミフォーマル の中庸の帯合わせが出てきたんです。
「 オリ・ソメ・ソメ・オリ 」 の呪文があまり効きすぎると ちょいカジュアル派の立場が弱くなっちゃいますよね。
新しい呪文 「 オリ・オリ 」「 ソメ・ソメ 」 もケースバイケースで アリっ ! ・・・ だと思います。
これは ぼくの個人的見解なので みなさんはじめ 同業のキモノびとのひとたちにもご意見お聞きしたいです。
是非是非 コメント お聞かせください。よろしくお願いします。 |(_ _)|
喜如嘉の芭蕉布 ~ 平良美恵子先生と再会できました!
2011年04月18日
蝉の羽 (せみのはね) のような かろやかさ・・・ 古来より伝わる古代原始布 の王さま・・・
琉球染織ファン あこがれの・・・ そう 、 喜如嘉 きじょか の 芭蕉布 です・・・!!!
芭蕉布の 平良 美恵子 先生 と 京都で お会いできたのでした・・・!

何年か前 呉服組合の視察で 沖縄を訪れたとき 平良美恵子先生 に 大変 親切にしていただき、
とっても 大きくて とっても 美味しい ハンバーガー を ご馳走に なったのです。 \(^▽^)/
個人的にも 芭蕉布 あこがれの大ファンであり 琉球染織ミーハーでもある ぼくは
尊敬する先生を前に もォ~ キンチョーメロメロなのでした・・・。 ~(=^□^=)~

『 ダキンフシー ( 竹の節 ) 』
ここで ふくひろの 芭蕉布たち を紹介させてください。 空に向かって ぐんぐん 伸びてゆく
青竹の節(ふし)を 表現した 繁栄 を意味する 絣図案 、 九寸名古屋帯です。
芭蕉布の着尺 キモノは なにはともあれ 最高峰なのですが、 まずは 名古屋帯からが おススメです。
お持ちの 絹上布、 麻上布 など 薄ものの織物に 芭蕉布の帯を締めると 琉球の風をまとった装いに・・・。

『 アケーズ ( 蜻蛉 とんぼ ) 』
蜻蛉(とんぼ) は どんどん まえへ まえへ 前進 する 縁起のよい勝ち虫 だと 先生に教えていただきました。
濃淡のかすりで 織り出された 蜻蛉の列をみていると ほんとうに大空を 雄大に 飛翔しているかのようです。

『 アササ ( 蝉 せみ ) 』
蝉(せみ)は 何度も 何度も 再生する 永遠の象徴 だと 平良先生は おっしゃいました。
たしかに 土のなかの生活も 昆虫とは思えないほど 長寿長命 ですものね・・・。大地の生命力 あふれてます。
しかし なにより この 琉球藍 で 織り出された えもいわれぬ 絶妙の色・・・!素晴らしくないですか・・・!?

琉球藍で 織られた アササ(蝉) は 本当に珍しいです。
ぼくは はじめて みました。 もォ~ メロメロ です・・・。
何度 眺めても 琉球藍を 含んだ 芭蕉の糸は 不思議な色ですね・・・
藍とグレーの 混じった色・・・なんて表現すると あまりにも単純すぎて・・・
なにか 年代を経た 鉱物の色 のような 深みがあります・・・
緯糸(よこいと) に 琉球藍 で染めた 芭蕉の糸を使うと この色が発現するそうです。
独特の色なので 淡い色の 上布 にも 濃い地色の 夏紬 にも 両方合いますね。
平良美恵子 先生に 滅多とない逸品を ご紹介いただき 感謝感激 です。
今回は 最初から 最後まで もォ~メロメロ しっぱなしなのでした~ (☆~☆)
琉球染織ファン あこがれの・・・ そう 、 喜如嘉 きじょか の 芭蕉布 です・・・!!!
芭蕉布の 平良 美恵子 先生 と 京都で お会いできたのでした・・・!
何年か前 呉服組合の視察で 沖縄を訪れたとき 平良美恵子先生 に 大変 親切にしていただき、
とっても 大きくて とっても 美味しい ハンバーガー を ご馳走に なったのです。 \(^▽^)/
個人的にも 芭蕉布 あこがれの大ファンであり 琉球染織ミーハーでもある ぼくは
尊敬する先生を前に もォ~ キンチョーメロメロなのでした・・・。 ~(=^□^=)~
『 ダキンフシー ( 竹の節 ) 』
ここで ふくひろの 芭蕉布たち を紹介させてください。 空に向かって ぐんぐん 伸びてゆく
青竹の節(ふし)を 表現した 繁栄 を意味する 絣図案 、 九寸名古屋帯です。
芭蕉布の着尺 キモノは なにはともあれ 最高峰なのですが、 まずは 名古屋帯からが おススメです。
お持ちの 絹上布、 麻上布 など 薄ものの織物に 芭蕉布の帯を締めると 琉球の風をまとった装いに・・・。
『 アケーズ ( 蜻蛉 とんぼ ) 』
蜻蛉(とんぼ) は どんどん まえへ まえへ 前進 する 縁起のよい勝ち虫 だと 先生に教えていただきました。
濃淡のかすりで 織り出された 蜻蛉の列をみていると ほんとうに大空を 雄大に 飛翔しているかのようです。
『 アササ ( 蝉 せみ ) 』
蝉(せみ)は 何度も 何度も 再生する 永遠の象徴 だと 平良先生は おっしゃいました。
たしかに 土のなかの生活も 昆虫とは思えないほど 長寿長命 ですものね・・・。大地の生命力 あふれてます。
しかし なにより この 琉球藍 で 織り出された えもいわれぬ 絶妙の色・・・!素晴らしくないですか・・・!?
琉球藍で 織られた アササ(蝉) は 本当に珍しいです。
ぼくは はじめて みました。 もォ~ メロメロ です・・・。
何度 眺めても 琉球藍を 含んだ 芭蕉の糸は 不思議な色ですね・・・
藍とグレーの 混じった色・・・なんて表現すると あまりにも単純すぎて・・・
なにか 年代を経た 鉱物の色 のような 深みがあります・・・
緯糸(よこいと) に 琉球藍 で染めた 芭蕉の糸を使うと この色が発現するそうです。
独特の色なので 淡い色の 上布 にも 濃い地色の 夏紬 にも 両方合いますね。
平良美恵子 先生に 滅多とない逸品を ご紹介いただき 感謝感激 です。
今回は 最初から 最後まで もォ~メロメロ しっぱなしなのでした~ (☆~☆)
反物 くる くる 5 〜でっちくん はじめて店頭に立つ!〜
2011年04月09日
反物 くるくる でっちくん。 今日は でっちくん が 生まれてはじめて 店頭に立つ日 なのです。
朝から キンチョーのあまり でっちくんの チキンハートは どっきんっ どっきんっ いまにも破裂しそうです。
おみせの ショーウィンドウを お客さまが みておられます。 でっちくんは オリの中のくまの ように
あっちこっち ウロウロしていましたが まさに 決死の覚悟を決めて ついに お客さまに 声をかけました・・・!
い っ・・・ い ら っ し ゃ い ま せ ぇぇぇ 〜・・・ !!
眼を血走らせ 噛み付かんばかりの でっちくんの気迫にびっくりして お客さまは あわてて立ち去っていきました。
ぽかん・・・ とひとり 取り残される でっちくん。 そりゃあ お客さま ビックリ しますよねぇ〜・・・。
あっ 次の お客さまです。 でっちくん こんどは ソフトに そして やや 親しげに 話しかけました・・・。
いやあ〜・・・ 今日は いい 天気 ですねえ ・・・
はァ・・ と 白い眼で お客さまは 向こうへ 行ってしまいました。またも ぽかんと ひとり取り残されるでっちくん。
ムリも ありません。 だって 空は シトシト 雨模様 なんですから・・・。 でっちくん 余裕なさすぎ です〜。
三人目のお客さまがウィンドウを見てます。でっちくん 意気込んでいくと お客さまの方から 訊(たず)ねてきました。
「 このキモノは 何歳ぐらいまで 着れるのかしら? 」 「 っっっ ・・・ ??? 」
みるみる カオが 真っ赤になる でっちくん。 あわてて 店の奥へ 逃げ込んでしまいました。
こんどは お客さまが ぽかんと ひとり取り残される始末・・・。 新米・ペーペーのでっちくんに答えようがありません。
だって でっちくん まだまだ キモノのキの字もわかってないんですから〜。 うーん、 困ったもんですねぇ〜。
こんなとき たよりになるのが やはり せんぱいくん です。 でっちくん 半ベソカキカキ せんぱいくんに訴えました。
「 お客さんとぉ〜 まともにハナシもできないしぃ〜 キモノのことも さーっぱり わかんないしぃ〜
一体 どーしたら いーんですかあ・・・!? 」 でっちくん くってかかって 涙・鼻汁 スゴイ剣幕です・・・。
相談に押しかけられて その上 逆ギレされてたら たまったもんじゃないですが まあまあとなだめるせんぱいくん。
「 オレやお前みたいな若いのが とってつけたような世間話 したって 誰も 聞いちゃくれんよ・・・。 」
「 だったら 何のハナシ するんですかあ? ボクは もともと ハナシするの 大の苦手なんですよお?
そんなに ハナシ得意だったら とっくのむかしに 落語家に弟子入りしてますよぉ〜 ! 」
「 ・・・お客さんは キモノを 見にきてんだから やっぱ キモノの ハナシを しなきゃあ・・・。 」
「 イイイイ ・・・ だから それは ボクには ムリだって いってんじゃないですかぁ〜 ! 」
「 アホゥ ! いま ウィンドウ に キモノと帯 どんだけだしとるんや ?! かぞえてみい ! 」
「 は ハイィ・・・ ひぃ ふう みぃ のぉ ・・・ ご、五点 ですぅ〜。 」
「 ええか? この五点の商品の名称・種類・季節・産地・セールスポイントその他モロモロをノートにかきだすんや!
そいで 今日中に 丸暗記するんや! 陳列変わるたんび なんべんも 、なんべんもやぞ ・・・! 」
「 ひ いいぃ・・・ なっ・・・なんべんもぉ ですかあぁぁ・・・? 」
「 当たり前や! お前の 一生分の 宿題じゃ〜 ! わかったかぁ・・・! 」 「 ハイ〜・・・! 」
まさに 門前の小僧 習(なら)わぬ 経(きょう) を 読む ・・・・
でっちくんの 一夜漬け・付け刃(つけやいば)の 心もとない知識 なれど だんだんと お客さまと 話が
してもらえるようになりました。返答に窮(きゅう)して 店の奥に逃げ込むコトも 相変わらずではありますが・・・。
それでも 幾度(いくたび)と ウィンドウの彩(いろど)り が移りゆくごとに
でっちくんのキモノの話も 少しずつ、 少しずつ 深みを増してゆくことでしょう・・・。
呉服屋さんは いくつになっても 勉強です。
でっちくんならずとも 一生分の宿題 を 楽しく やっていきたいものです。
反物 くる くる でっちくん 。 まだ まだ 先は 長いですよぉ~・・・。
朝から キンチョーのあまり でっちくんの チキンハートは どっきんっ どっきんっ いまにも破裂しそうです。
おみせの ショーウィンドウを お客さまが みておられます。 でっちくんは オリの中のくまの ように
あっちこっち ウロウロしていましたが まさに 決死の覚悟を決めて ついに お客さまに 声をかけました・・・!
い っ・・・ い ら っ し ゃ い ま せ ぇぇぇ 〜・・・ !!
眼を血走らせ 噛み付かんばかりの でっちくんの気迫にびっくりして お客さまは あわてて立ち去っていきました。
ぽかん・・・ とひとり 取り残される でっちくん。 そりゃあ お客さま ビックリ しますよねぇ〜・・・。
あっ 次の お客さまです。 でっちくん こんどは ソフトに そして やや 親しげに 話しかけました・・・。
いやあ〜・・・ 今日は いい 天気 ですねえ ・・・
はァ・・ と 白い眼で お客さまは 向こうへ 行ってしまいました。またも ぽかんと ひとり取り残されるでっちくん。
ムリも ありません。 だって 空は シトシト 雨模様 なんですから・・・。 でっちくん 余裕なさすぎ です〜。
三人目のお客さまがウィンドウを見てます。でっちくん 意気込んでいくと お客さまの方から 訊(たず)ねてきました。
「 このキモノは 何歳ぐらいまで 着れるのかしら? 」 「 っっっ ・・・ ??? 」
みるみる カオが 真っ赤になる でっちくん。 あわてて 店の奥へ 逃げ込んでしまいました。
こんどは お客さまが ぽかんと ひとり取り残される始末・・・。 新米・ペーペーのでっちくんに答えようがありません。
だって でっちくん まだまだ キモノのキの字もわかってないんですから〜。 うーん、 困ったもんですねぇ〜。
こんなとき たよりになるのが やはり せんぱいくん です。 でっちくん 半ベソカキカキ せんぱいくんに訴えました。
「 お客さんとぉ〜 まともにハナシもできないしぃ〜 キモノのことも さーっぱり わかんないしぃ〜
一体 どーしたら いーんですかあ・・・!? 」 でっちくん くってかかって 涙・鼻汁 スゴイ剣幕です・・・。
相談に押しかけられて その上 逆ギレされてたら たまったもんじゃないですが まあまあとなだめるせんぱいくん。
「 オレやお前みたいな若いのが とってつけたような世間話 したって 誰も 聞いちゃくれんよ・・・。 」
「 だったら 何のハナシ するんですかあ? ボクは もともと ハナシするの 大の苦手なんですよお?
そんなに ハナシ得意だったら とっくのむかしに 落語家に弟子入りしてますよぉ〜 ! 」
「 ・・・お客さんは キモノを 見にきてんだから やっぱ キモノの ハナシを しなきゃあ・・・。 」
「 イイイイ ・・・ だから それは ボクには ムリだって いってんじゃないですかぁ〜 ! 」
「 アホゥ ! いま ウィンドウ に キモノと帯 どんだけだしとるんや ?! かぞえてみい ! 」
「 は ハイィ・・・ ひぃ ふう みぃ のぉ ・・・ ご、五点 ですぅ〜。 」
「 ええか? この五点の商品の名称・種類・季節・産地・セールスポイントその他モロモロをノートにかきだすんや!
そいで 今日中に 丸暗記するんや! 陳列変わるたんび なんべんも 、なんべんもやぞ ・・・! 」
「 ひ いいぃ・・・ なっ・・・なんべんもぉ ですかあぁぁ・・・? 」
「 当たり前や! お前の 一生分の 宿題じゃ〜 ! わかったかぁ・・・! 」 「 ハイ〜・・・! 」
まさに 門前の小僧 習(なら)わぬ 経(きょう) を 読む ・・・・
でっちくんの 一夜漬け・付け刃(つけやいば)の 心もとない知識 なれど だんだんと お客さまと 話が
してもらえるようになりました。返答に窮(きゅう)して 店の奥に逃げ込むコトも 相変わらずではありますが・・・。
それでも 幾度(いくたび)と ウィンドウの彩(いろど)り が移りゆくごとに
でっちくんのキモノの話も 少しずつ、 少しずつ 深みを増してゆくことでしょう・・・。
呉服屋さんは いくつになっても 勉強です。
でっちくんならずとも 一生分の宿題 を 楽しく やっていきたいものです。
反物 くる くる でっちくん 。 まだ まだ 先は 長いですよぉ~・・・。